赤い糸の結び方/村田侑衣
10分で読めるホラー風恋愛小説
運命の赤い糸というのは二人の自由を奪う鎖なのだと思う。結ばれることを約束してくれる代わりに繋がった相手と距離を取ることが出来なくなる。そんな鎖。
関係を先に進めたい私と現状維持を望む翔一。平行線を辿る私たち二人の考えはきっと、いつまで待っても交わらないのだろう。出会って二年。仲が悪くなったとは思わない。が、良くなったとも思わない。何も変わらないことがただ不安で、変えようという様子がないことが不満だった。
「お待たせいたしました。アイスコーヒーと抹茶ラテでございます」
柔らかい声が耳に届いた。ネガティブなことばかりが浮かぶ思考を一旦止めて、声の出所に目をやる。大学生くらいに見える可愛らしい女の子。トレンチを片手に微笑むその子はテーブルの上にグラスとカップをそっと置いて深々と頭を下げた。
「ごゆっくりどうぞ」
落ち着いた雰囲気の店内。丁寧な接客。通りにいくつか並ぶカフェの中で一番人気という話は本当なのだろう。そんなことを考えながら背中を見送る。
私の視線を無視して手元の携帯電話を眺めていた翔一はようやく顔を上げた。
「あ、ごめんごめん。部長からのメールでさ。急ぎじゃなかったんだけど」
「ううん。大丈夫」
申し訳なさそうな顔に向かってそう言ってから笑顔を作った。少しでいいから気にして欲しい……。本音は隠しておくことにした。
「仕事でしょ? 気にしないで。というか、なんでおかわりはアイスなの?」
「待ってる間ゆっくり飲もうと思ってホットにしただけ。深い意味はないよ」
そう言って笑った翔一は氷を鳴らしながらグラスを口元に運んだ。
「待たせてごめん……でも急いで準備したんだよ? あ、期待はしないでね?」
「いや、期待してる。わざわざ俺を部屋から追い出して準備してくれたんだから。きっと凄い料理とサプライズが待ってるはず」
唇の隙間をすり抜けていくアイスコーヒー。揺れる喉仏に一瞬見惚れる。
「見られたくなかっただけだから……料理苦手なの知ってるでしょ?」
「さあ?」
「もう……本当に良かったの? 誕生日だし何でもご馳走するつもりだったのに」
「いいんだよ。たまには佳奈の手料理が食べたいなって」
グラスを置いた翔一はニヤッと笑った。少年のような顔がたまらなく愛おしい。
「同棲してくれたら毎日頑張って作るつもりだけど?」
「うーん。たまにでいいかな」
「……それ、手料理と同棲のどっちを拒否してる?」
「拒否なんかしてないよ。毎日頑張って作ってもらうのは申し訳ないなと思って」
「ふーん」
持っていたカップを置いた私は膝の上の左手を眺めた。先ほど貼った絆創膏を右手の人差し指で優しく撫でる。痛みを感じたのは切り口ではなく心の方だった。
私の頑張りが足りないのかもしれない。今までそう思っていた。だが、どんなに頑張っても想いは届かない。
「あ、そういえばこれ何? 棚の上に置いてあったんだけど」
「分からない。ポストに入ってた」
「へー。そうなんだ。これ、リングカタログだよね?」
「多分そう。誰が入れたんだろうな」
何かに縛られることを、不自由を嫌う翔一。きっとこのまま待っているだけでは何も変わらない。私が何か行動を起こさないと先には進めない。
「そろそろ帰ろっか。お腹空いてきたし。手料理楽しみだなー」
「うん」
だから今日――。
伝票を持って立ち上がった翔一は「払ってくる」と言ってレジの方に向かった。
「ちょっと待って。今日は私が払うよ」
すぐに立ち上がってレジに向かう。会計を済ませて店を出た私は翔一の背中を早歩きで追いかけた。
置き忘れていたプレゼントを持って一足先に部屋に入った私は、用意した木箱を眺めて考えた。
左手の小指から伸びる赤い糸。見えなくて……繋がれていなくて本当に良かった。どれくらいの長さなのかは知らないが、もし繋がれていたら少なからず翔一の自由を奪っていたのだろう。そんなことを望んではいない。
私たちなりの方法でこれから結べばいいだけ。何の問題もない。
「え、すご! これ全部佳奈が作ったの?」
リビングに入ってきた翔一はテーブルに並んだ料理を見て驚いた顔をした。
「びっくりした? 頑張って作ったんだよ?」
「本当に美味しそう。正直、ここまで出来るとは思ってなかった」
「その言い方は酷くない? たしかに期待するなとは言ったけど」
いつもの椅子に腰を下ろした翔一が浮かべた優しい笑み。
「冗談だよ。ありがとう」
大好きなこの笑顔のためならきっと私は何だって出来る。
「本当に冗談? まあいいや。食べよっか。ビールでいいよね?」
「あのさ」
そう言って翔一は肩にかけていた鞄に手を入れた。「これ」出てきた右手にはリングケースが乗っていた。大きく深呼吸をしたあと、左手でゆっくりと開いていく。
「……え? 指輪?」
「そう。そろそろ、さ。結婚してみるのもいいんじゃないかなって」
カタログに付けた印に気付いてくれたのだろう。欲しかった指輪が翔一の手の上で光っている。
「……一緒に住むことすら嫌なのかと思ってた」
「そんなこと言ってないだろ?」
「だって……」
「ほらテッシュ。そんな泣くなよ」
「ありがとう。まさかプロポーズされるとは思ってなくて……」
「よく言うよ。カタログ用意して丸まで付けといて。とりあえず乾杯でもしよっか。ビール取ってくるよ」
そう言って立ち上がった翔一はキッチンの方に向かった。
「私じゃないよ?」
冷蔵庫を開けた際に出た音だろう。缶ビールが体をぶつけ合う音が聞こえてきた。
「はいはい、わかった。そういうことに……何これ?」
「何って何が?」
どうやら気付いてくれたようだ。
「この小っちゃい木箱」
私からのプレゼントに。
次に聞こえてきたのは悲鳴のような短い叫び声だった。
「おい! これ……」
そう言いながら慌てた様子でリビングに戻ってきた翔一。手にはしっかりプレゼントを持っていた。蓋の開いた木箱。中には左手の小指が入っている。
「何これ……」
赤い蝶々を纏った小指。束縛なんてしない。そんなメッセージを込めた私の分の小指。
……これでようやく一歩踏み出すことが出来る。
今、結ぶからね。
押入れの扉を開いた私を、部屋の明かりが祝福してくれているような気がした。
〈了〉

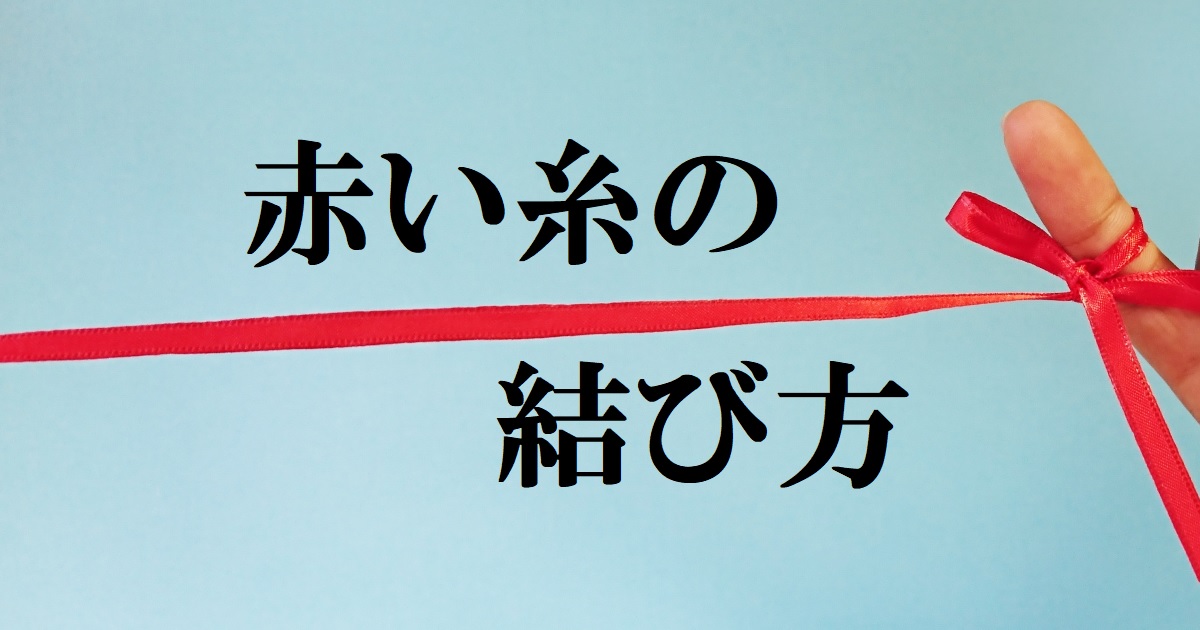
コメント